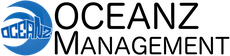国土交通省は20日、7月1日時点の「都道府県地価調査」の結果を公表した。全国平均の地価は、全用途で0.6%の下落にとどまり、前年からの下落幅は0.3ポイント縮小した。
うち、住宅地は、0.8%の下落で、下落幅が0.2ポイント縮小。商業地は、0.0と横ばいとなり、8年連続の下落から脱した。住宅地は継続する低金利環境や住宅ローン減税などによる住宅需要の下支え効果もあり、下落幅が縮小。
一方、商業地は外国人観光客増加による店舗・ホテル需要の高まりと、主要都市でのオフィス空室率低下による収益性の向上など、旺盛な不動産需要が地価を押し上げた。
三大都市圏の住宅地をみると、変動率は0.4%上昇。上昇幅は、前年並みとなった。東京圏が前年同様、+0.5%、大阪圏も前年同様、0.0%だったのに対し、名古屋圏は+0.5%(前年+0.7%)で上昇幅が縮小した。
一方、三大都市圏の商業地については、2.9%上昇し、4年連続の上昇。上昇幅は0.6ポイントだった。東京圏が+2.7%(+2.3%)、大阪圏が+3.7%(+2.5%)、名古屋圏が+2.5%(+2.2%)と、いずれも上昇幅を拡大・加速。特に大阪圏の伸びが目立った。
一方、地方圏をみると、札幌市、仙台市、広島市、福岡市の地方主要4市は、住宅地が+2.5%(+1.7%)、商業地が+6.7%(+3.8%)と、三大都市圏を上回る上昇となった。地価水準が三大都市圏より割安で、人口増加による住宅需要の増大、交通インフラの整備、再開発事業、インバウンド増加などが要因とみられる。
ただ、そのほかの地方圏では、住宅地が△1.4(△1.6)、商業地が△1.5(△1.9)と、下落幅が縮小したものの、下落を継続。山間部や沿岸部など、利便性で劣る地点では下落幅の拡大がみられ、地方の二極化が進んだ。
都道府県別にみると、住宅地で、上昇した都道府県の数は前年比3減少して5となった。神奈川県は、前年の+0.1%から△0.2%に。県西部での下落幅拡大と、横浜市・川崎市での上昇率縮小が影響した。横浜市や川崎市では、駅から遠いバス利用の住宅地で下落に転じた地点がある。ただ、大阪府は+0.0%から△0.0%と、小数点以下2ケタ台の僅かな下落。ほぼ横ばいともいえ、大阪市に近い地区では上昇傾向が続くが、郊外で下落もみられた。
同じく千葉県も+0.0%から△0.0%と僅かな下落だったが、栄町、我孫子市、柏市などの下落拡大を反映した。一方で、住宅地で2%以上下落した都道府県の数も、前年比5減少して8となり、減少分は下落率2%未満に収まった。また、商業地は、上昇した都道府県数が前年比3増え、15に。2%以上の下落では、同8減り、13となった。
(提供:日刊不動産経済通信)